出典:[amazon]正岡子規 名作全集: 日本文学作品全集(電子版) (正岡子規文学研究会)
「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」という句を詠んだ、正岡子規をご存じですか?松山に生まれ、明治の文明開化とともに人生を歩んだ子規。彼は、過去のものになろうとしていた俳句、短歌などを蘇らせ、世界の文学に通じるすばらしい近代詩歌の基礎をつくることに貢献しました。結核にかかり、病と闘いながら文学を確立し、生をみつめる輝かしい作品を数多く生み出した正岡子規とはどのような人物だったのでしょうか?今回は、生涯に1万8千句以上の俳句を残し、日本近代文学の革新を成し遂げた明治の文学者・正岡子規の生涯についてご紹介します。
正岡子規の生涯

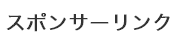
正岡子規の本名
正岡子規の本名は、正岡常規(まさおかつねのり)です。
幼名を処之助(ところのすけ)といいましたが、のちに、升(のぼる)と改名します。
誕生から学生時代
正岡子規は、(慶応3年)1867年10月14日(新暦)に現在の松山市に生まれました。その翌年、元号は慶応から明治に改まり、子規の人生は明治とともに進んでいくこととなります。
父の隼太常尚(はやたつねなお)は松山藩士で、母の八重は藩の儒者、大原観山(かんざん)の長女でした。1870年には、妹の律が生まれます。1872年に父が亡くなり、翌年から、祖父の大原観山の漢学塾に通い素読を習いはじめます。そして1878年には、漢詩をつくりはじめました。
1880年、松山中学に入学すると、漢詩のグループ「同親会」を結成します。1882年には、政治に関心をよせ、政談演説に熱中しました。翌年、受験勉強のため松山中学を中退し、叔父の加藤拓川(たくせん)を頼って上京し、共立学校に入学します。その後、1884年に東京大学予備門(後の第一高等中学校)に入学しました。そしてすぐにベースボールに出合い、始めます。
1885年7月に初めて帰郷し、歌人に歌を習い俳句を作りはじめました。しかし、1888年8月、江の島旅行中に初めて喀血します。翌年1月、子規は第一高等中学校の学生として、夏目漱石と出会いました。そしてその年の5月には、2度目の喀血を経験し、結核と診断されます。その夜、再び喀血し「時鳥」という題で4、50句の俳句を詠み、そこから「子規」のペンネームを使いはじめました。
1890年に帝国大学文科大学哲学科に入学しますが、翌年哲学科から国文科に転科します。
そして「俳句分類」をはじめ、古典俳句の大がかりな分類にとりかかりました。1892年に、叔父の紹介で知り合った陸羯南(くがかつなん)が社長の新聞「日本」で、子規は、俳句革新の第一歩として「獺祭書屋俳話(だっさいしょおくはいわ)」の掲載をはじめます。その後、学年末試験に落第し、退学を決意します。11月に母と妹を東京に呼び寄せ、12月に新聞「日本」に入社しました。そして翌年3月、帝国大学を退学します。
新聞記者時代
1894年に生涯を終えるまで暮らした、上根岸の住居にうつります。そして、文化記事を主体にした小新聞「小日本」が創刊されることになり、子規は編集責任者に抜擢されました。その仕事をするなかで出会った画家の中村不折から、西洋絵画の写実主義について学んだことをきっかけに、これ以降「写生」の句が増えていきます。写生は、自分の目で見てかんじたことを素直に表現するというものです。そのことで、物事の本質をとらえることができると子規は考えました。
1895年、周りから反対されながらも、日清戦争の従軍記者として遼東半島の金州へ赴きます。しかし、その後まもなく講和条約が締結され、戦争は終わりをむかえました。子規は、その帰国の船中で大量喀血し、神戸病院に入院しますが、一時重体に陥ります。その後、須磨保養院で療養し、松山に帰省しました。そして、たまたま松山にいた、親友の夏目漱石の下宿「愚陀仏庵」でともに暮らし、子規は郷里で52日間の静養生活をおくります。
しかし、自分はまだ何もなしえていないと、漱石が引き留めるも、子規は上京を決心します。上京の途上、奈良に寄り、法隆寺の茶店で詠んだのが「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」という俳句です。これは、「鐘つけば 銀杏散るなり 建長寺」という、漱石が詠んだ俳句に返したものではないかといわれています。
そして、東京に戻るとすぐ10月に「俳諧大要」を新聞「日本」に掲載し、俳句に力を入れていきました。
病床時代
1896年2月ごろから腰が腫れて痛みがひどく、床に臥せる日が多くなります。3月には、結核が進行して骨を腐らせる、脊椎カリエスと診断されました。しかし、病床で作品をつくるようになってからの正岡子規は、さらに文学への情熱を残り少ない命とともに燃やしていくのです。このころから「即時」の句が増えてきます。これは、自分の句と物事のあいだに不要なものを入れず、そのとき起こっていることを、ありのまま詠むという方法です。
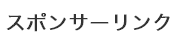
1897年、俳句雑誌『ほとゝぎす』が、郷里松山で友人の柳原極堂によって創刊されました。これは、子規の理想とする俳句を実現するための雑誌です。翌年、拠点を東京に移し、子規の協力で「ホトトギス」第一号が高浜虚子によって刊行され、現在もつづいています。
そして、「歌よみに与ふる書」を発表し、短歌の革新をはじめます。古典に息をふきこみ、いつの時代にも通用する、西洋の文学に負けない日本文学の礎をつくろうとしました。
1901年、体力がなくなってきた子規は、一度筆に含ませた墨で書き切れる長さの1行から20行までの文章を、随筆「墨汁一滴」と題して新聞「日本」に連載しはじめます。床に臥せた彼の目線で病を楽しみ、俳句や短歌、彼の暮らしや病状、社会批判や論評など様々なことを書きました。
そして、病状が悪化してくると、個人的な日記「仰臥漫録(ぎょうがまんろく)」を書き始めます。闘病生活のなかで食べたもののスケッチや、出来事、会った人など、おおくのことを詳細に記録していきました。
1902年5月には、新聞「日本」に随筆「病牀六尺」を連載開始し、亡くなる2日前まで書き続けます。六尺の病床から見たものごとを、そのまま詳しく書いたことが、かえって壮烈な人生を懸命に生きる姿を浮き上がらせ、物事に深みをもたせることとなりました。
そして亡くなる前日、「糸瓜(へちま)咲て 痰のつまりし 仏かな」など「絶筆三句」を書きのこし、正岡子規は1902年9月19日、午前1時ごろ死去します。満34歳11カ月でした。
正岡子規の性格を物語るエピソード

ベースボールに熱中
子規は、ほかのスポーツには全く興味がありませんでしたが、ベースボールには大変関心をもち、夢中になってプレーしていました。まだアメリカからベースボールが入ってきて間もないころ、選手として活躍しています。
帰郷した際、地元のひとにベースボールを教えたり、新聞「日本」に試合方法やルールなどを詳しく解説し、用語を翻訳した記事を掲載したりしました。
例えばランナーを「走者」、バッターを「打者」、フライを「飛球」、デッドボールを「死球」などと訳し、これらは現在でも使用されています。
そして、ベースボールの詩歌を新聞「日本」にたびたび掲載しました。また未完ですが、おそらく日本初であろうベースボール小説も書いています。このようにして、子規は現在の野球の普及に貢献しました。
親友 夏目漱石との強い絆
夏目漱石とは親友の仲で、子規が重い病のなか会ったり、頻繁に手紙を交わしたりと、たびたび交流がありました。
たまたま松山に赴任していた漱石の下宿「愚陀仏庵」で、子規は結核の療養をしました。ここで、漱石と子規は50日あまりを、ともに暮らしています。そのときに、子規に俳句を添削してもらおうと、地元の俳句仲間が多く訪ねてきました。そして、漱石も一緒にみんなで句会をひらき、学びあったということです。
また、夏目漱石の「漱石」は、正岡子規の数あるペンネームのひとつでした。
子規が亡くなったあと、漱石は『吾輩ハ猫デアル』中編の序文で彼について書いたり、この小説のなかに登場させたりしています。
そして、俳句雑誌「ホトトギス」に子規についての文章を寄せていました。
死因
結核が進行して、脊椎カリエスを発症し、それが原因で1902年9月19日に34歳11か月で亡くなりました。彼が亡くなるまで過ごした住居は再建され、現在「子規庵」として公開されています。
まとめ
今回は、正岡子規の生涯についてご紹介しました。34年という短い人生のなかで、病とともにありながら、俳句、短歌、随筆、論評、新体詩、小説など様々なジャンルで、多くの作品を残した正岡子規。「写生」や「即時」という表現法をつかうなどして古典詩歌を新しくして広め、古今東西に通用する日本文学の礎を築き、庶民の手に俳句や短歌を戻しました。西洋からの新たな文学が入ってくるなかで、病床にありながら俳句の本質を変化させ、後世に残すことに貢献しました。子規の作品には親しみやすく、味わい深いものが数多くありますので、青空文庫などでこの機会に読んでみてはいかがでしょうか。


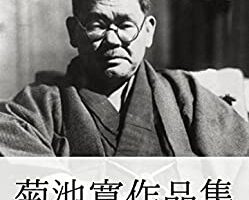



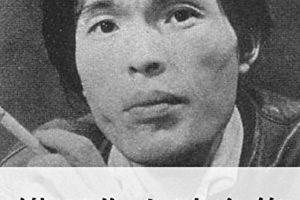








コメントを残す