4月になると新入社員が入社したり、異動があったり、春は出会いと別れが多い季節ですよね。ところで新年度の挨拶をメールでするときのルールを知っていますか?
また新年度は何かとスピーチの機会も増えてきます。メールもスピーチもいきなり言われると困るという人も多いですよね。今回はいざというときに困らないように新年度の挨拶メールや印象に残るスピーチをご紹介します。
新年度に挨拶メールを送るのはどんなとき?
新年度の挨拶メールと聞いて、どんな人が送るの?と思った人もいるでしょう。
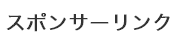
4月の新年度の挨拶メールは、新入社員や新しい部署で先輩や上司から仕事を引き継いだときなどにするメールです。
12月の年末の挨拶や、1月のお正月明けの新年の挨拶はみんながするものですが、新年度の挨拶は全員がするわけではありません。
新年度に送る挨拶メールのルール

新年度の挨拶メールは季節の表現を入れながら、長すぎずかつ丁寧な文書にすることが大切です。
新年度の挨拶メールの書き方は、書き出しと結語がポイントになってきます。
一般的にメールの場合は、新入社員など初めてのときは「はじめまして。」や「突然のご連絡失礼いたします。」と書き始めるのがいいでしょう。
また、先輩から仕事を引き継いだことを取引先に伝えるときには、「いつもお世話になっております。」と書き始めても大丈夫です。
会社として初めて連絡を取るわけではないので、はじめましてだと少し違和感がありますよね。
さらに丁寧に書くのであれば、手紙と同じように書きます。
書き始めは「拝啓」、結語は「敬具」を使うのが一般的です。
また季節感のある表現を入れることが大切です。
いくつか例文を見ていきましょう。
書き出し
「拝啓 陽春の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
「拝啓 春陽の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」
季節感のある言葉とは、4月の時候の挨拶を使いましょう。
結語
「新年度を迎えなにかとお忙しいと存じますが、ますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。」
「季節の変わり目ですのでどうぞご自愛ください。」
結びの言葉は、挨拶の内容によって変わってきますが、基本的には相手を思いやる表現がいいでしょう。
ちなみに間違いやすいのが「ご自愛ください。」という言葉の使い方です。
「お体をくれぐれもご自愛ください。」なんていう表現も見かけますが、「ご自愛ください=体を大事にしてください」という意味なのでお体といった言葉をつけるのは間違っているので気をつけましょうね。
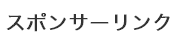
新年度にスピーチをするのはどんなとき?

新年度はスピーチをすることも多いですよね。
歓送迎会では必ずと言っていいほどあるでしょう。
新入社員は自己紹介のスピーチを、先輩や上司のみなさんはエールを送ることになると思います。
どちらも慣れていないとちょっと緊張してしまいますよね。
新年度のスピーチをするときのポイント
新年度のスピーチをするときのポイントを見ていきましょう。
スピーチは長すぎないことが大切です。
新入社員の場合
新入社員の自己紹介のスピーチの場合は、「簡単な自己紹介」と「今後の抱負」を語りましょう。
名前と「よろしくお願いします。」だけでは、印象が悪いですよ。
簡単な例文を確認しておきましょう。
「この度〇〇部に配属になりました、〇〇と申します。
皆さんと一緒に仕事ができることを大変うれしく思います。
みなさんにご迷惑をおかけすることもたくさんあると思いますが、一日でも早く仕事を覚えて頑張ります。
よろしくお願い致します。」
このような挨拶をイメージしておけば大丈夫です。
印象に残るスピーチをする場合は、学生のときの部活や特技などを簡単に紹介すると、「〇〇の子!」と覚えてもらえますよ。
また自分の好きな名言やモットーなどを簡単に紹介するのも印象が強くなります。
先輩や上司の場合
先輩や上司として迎える側の場合のスピーチは「歓迎の言葉」と「職場の紹介」、さらに「不安を解きほぐす言葉」が添えられるといいでしょう。
くれぐれも長くなったらダメですよ!
簡単な例文を見ておきましょう。
「新入社員のみなさん、入社おめでとうございます。
みなさんを仲間としてお迎えできて本当にうれしく思います。
戸惑いや不安な気持ちも多いと思いますが、〇〇部はみんな仲のいい頼りになる先輩ばかりなので、わからないことはなんでも聞いてください。
そしてこの初心の気持ちを忘れずに学んでいってください。
みなさんの活躍を期待しています。」
このような挨拶をベースに社風にあった印象に残るスピーチをしましょう。
新年度に向けて準備をしよう!

新年度は何かと準備が必要です。
いきなり言われて焦らないように、メールの基本や挨拶の仕方などを予め学んでおきましょう。
新入社員はわからなければもちろん先輩に聞いてみるのもいいでしょう。
くれぐれもわからないことをそのままにしないこと!
「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」って言いますからね…。














コメントを残す